[quads id=1]
ADHDの子どもへの対応方法について、検索中ですね。
ADHDとは、発達障がいのひとつ。そのため、大人が「できて当たり前!」と思っていることが、ADHDの子どもにとっては難しいことがあります。
保育園や幼稚園で過ごす時間は、人格形成にも関係する大切な時間。
しかし、「そもそも、ADHDってどんな症状なの?治るのかな?」「どうやって対応したらいいんだろう」と感じているかもしれませんね。
そこでここでは、保育士が知っておきたい「ADHDの子どもへの対応方法」を詳しくご紹介。ADHDはどんな症状で、どんなトラブルが起きやすいのか、分かりやすく説明します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
ADHDとは、発達障がいのひとつ

ADHDは、「Attention Deficit Hyperactivity Disorder」という発達障がいのひとつ。日本での正式名称は、「注意欠如・多動性障がい」と言います。
ADHDの主な症状は、次の3つです。
- 不注意(集中力が続かない)
- 多動性(じっとしていられない)
- 衝動性(考えずに、行動してしまう)
これらの特徴の現れ方で、ADHDは3つのタイプに分けられます。次にADHDはどんなタイプに分けられるのか、具体的な症状も合わせて説明します。
ADHDには、3つのタイプがある
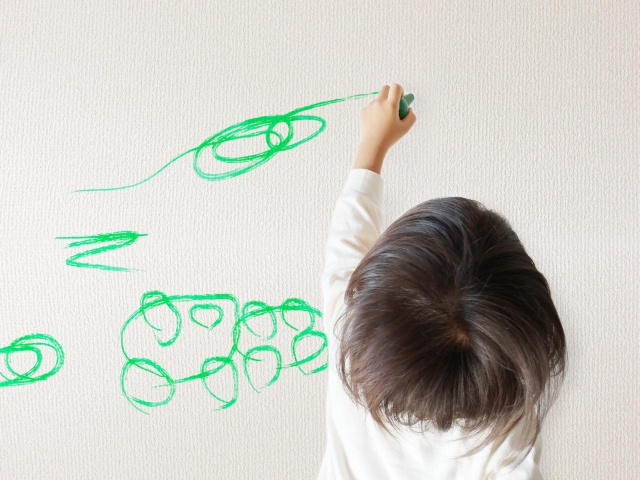
ADHDの子どもは、次の3つのタイプに分けられます。
- 不注意が目立つタイプ
- 多動性、衝動性が目立つタイプ
- 不注意と多動性、衝動性が混じった、混合タイプ
どんな症状が見られるのか、それぞれ具体的に説明します。
1.不注意が目立つタイプ
不注意が目立つタイプは、集中力が続きません。忘れ物が多く、ものをなくしたり、部屋の片付けが苦手。すぐ他のものに興味を移すため、人の話を聞けないことも多くあります。
2.多動性や衝動性が目立つタイプ
多動性や衝動性が目立つタイプは、とにかく体を動かすことが好きです。落ち着きがなく、すぐ席を立ってしまいます。また感情を抑えられず、ささいなことで友達に手を出してしまうことも。そのため、「乱暴な子」と思われやすいタイプです。
3.不注意と多動性・衝動性が混じった、混合タイプ
混合タイプは、不注意と多動性、衝動性の3つの特徴を持っています。忘れ物も多く、じっとしていることが苦手です。感情のまま行動し、順番を守れないことも。ADHDの子どもの80%が混合タイプと言われています。
このように、ひとことで「ADHD」といっても個人差があります。
どうしてこのような症状が出てくるのか、決定的な原因は分かっていません。有力な説は、行動をコントロールする脳の働きに偏りがあると考えられています。そのため、「親の育て方が悪いから、ADHDになった」という考えは間違いです。
ただし、接し方や対応に気をつけることで、症状を改善することもできます。ここからは、ADHDの子どもに 接するときに、気をつけるべきポイントを紹介します。
ADHDの子どもへの対応で、気をつけるポイントは3つ

ADHDの子どもへの対応で、気をつけるポイントは次の3つです。
- 本人への支援
- 集団的な支援
- 保護者への支援
本人への支援だけでなく、教室の環境や友だち、さらに保護者へ支援も行うことで、ADHDの子どもものびのびと過ごすことができます。
「3つもあるの?」と思うかもしれませんが、ポイントは難しくありません。実際にどんなことを行えばいいのか、次から紹介します。
本人への支援
まずは、ADHDの子ども本人への支援を紹介します。
本人への支援は、主に次の5つです。
- 説明するときは、絵を使う
- 集中できる時間に合わせて、休憩をはさむ
- 感情的に叱らず、穏やかに「代替案」を伝える
- 約束ができたら、とにかくほめる
- 単に注意を引きたくて騒いでいるときは、無視も有効
それぞれ具体的に、説明していきます。
1.説明するときは、絵を使う
ADHDの子どもに何かを説明するときは、絵を使いましょう。
人は、目からの情報がもっとも受け入れやすいもの。とくに集中するのが苦手なADHDの子どもは、言葉だけの説明では分かりにくいことがあります。
例えば、イスの座り方を説明するとき、イスのイラストを描いて注意するポイントに、⚪︎をつけておきましょう。「足は床につける」「頭のてっぺんは天井を向く」など、具体的かつ短い言葉で説明すると、伝わりやすくなります。
自分で書くのが難しいときは、パソコンからイラストを探してくるのも良いでしょう。
2.集中できる時間に合わせて、休憩をはさむ
みんなでお絵かきなど課題をしているときは、子どもが集中できる時間に合わせて、適度に休憩をはさんであげましょう。
ADHDの子どもは、他のことに気を取られやすいため、長い時間集中できません。集中が切れるタイミングで休憩を入れることで、気持ちを切り替えやすくなります。
例えば、じっと机に座って作業するのであれば、体を動かしてあげましょう。ADHDの子どもは、体を動かすのが好きなことが多いもの。適度に体を動かすことで、ストレスをためにくくなります。
3.感情的に叱らず、穏やかに「代替案」を伝える
子どもを叱るときは、感情的に叱らず、穏やかに「次からはこうしよう」と代替案を伝えてあげましょう。
ADHDの子どもは感情を抑えたり、言葉にして気持ちを伝えることが苦手です。そのため、感情のまま暴れてしまうことが多くあります。しかし、止めようとした保育士も大声を出して叱ってしまうと、パニックを起こしてヒートアップしてしまうことも。
まずは、子どもを落ち着かせてあげましょう。もし、原因になったオモチャや人物がいれば、その場を離れて子どもの話を聞くと落ち着きやすくなります。
落ち着かせるポイントは、しっかり子どもの感情を受け入れること。「オモチャがほしかったのに、手に入らなくて悔しかったんだね」と子どもの気持ちを言葉にすれば、子どもも「先生は、分かってくれたんだ」と話を聞いてくれるようになります。
その上で、「次からは、貸してほしいって言ってみてごらん」と暴れる以外の方法を伝えてあげましょう。また「お友達を叩いちゃうかもしれないから、暴れるのはやめようね。先生は○○くんが優しい子って知ってるから、みんなから乱暴者って思われるのは悲しいな」と暴れてはいけない理由も合わせて説明しましょう。
感情を抑えられないのは、ADHDの特徴です。うまくいかないからと言っても、焦らずにじっくりと取り組みましょう。
4.約束を守れたら、とにかくほめる
子どもが約束を守れたら、とにかくほめてあげましょう。
ほめることは、子どもにとってうれしいことです。何か行動をした後に、うれしいことや良いことがあると、何度もその行動をくり返すようになります。
例えば、「ほしいものがあるときは、貸してとお願いする」と約束したとしましょう。子どもが約束を守り「そのオモチャを貸して」と言っていたら、すかさずほめます。ほめるときは、「○○ちゃん、オモチャ貸してって言えたね!すごいね!○○ちゃんが約束守れて、先生もうれしい!」というように、自分自身の感情も込めると気持ちが伝わりやすいです。
他にも、カードを用意して「約束を守れたら、シールを1枚はる」「10枚たまったら、ご褒美がもらえる」というポイント制にしても良いでしょう。子どもの好ましい行動を増やすことができます。
5.単に注意を引きたくて騒いでいるときは、無視も有効
子どもが単に大人の注意を引きたくて大声を出しているときは、無視するのも有効です。
子どもは、自分が行動した後に思うような結果が出ないと、その行動をくり返そうとはしません。「あ、注目してほしくて騒いでいるな」と分かったら、声はかけずに遠くで見守っていましょう。
もし、注意を引きたくて騒いでいるときに保育士が声をかけたら「大声を出せば、先生が来てくれる」と学習してしまいます。「大声を出しても、先生は来ない」と子どもが理解すれば、自然と騒ぐ回数は減っていくもの。声をかけるだけでなく、あえて離れることも子どもへの支援になります。
以上が、ADHDの子ども本人への支援方法です。
どれも、まずは子どもの好みや集中できる時間を、しっかり把握することが大切。
子どもの様子や反応を見て、「どんなほめ方が、1番うれしいか」「お絵かきだと10分集中できているな」など、メモしておくと良いでしょう。最初はなかなかうまくいかないかも知れませんが、「どうしてできないんだろう」というよりも「どうしたらできるかな?」と考えるのがポイント。
じっくり子どもと向き合っていくという気持ちがあれば、子どもも信頼してくれるようになりますよ。
[quads id=1]
集団的な支援
ADHDの子どもを担当するときは、個人への対応だけでなく、教室の環境など、集団的な支援も行いましょう。
集団的な支援とは、主に次の3つです。
- 教室はシンプルにする
- 周りの子どもに理解を求める
- 他にも担当する先生がいる場合、接し方を共有する
それぞれ説明していきます。
1.教室はシンプルにする
ADHDの子どもを担当するときは、教室はシンプルにしておきましょう。
ADHDの子どもは、いろんなことに気が散りやすいもの。教室をシンプルにすると気になる対象が減るため、集中しやすくなります。
例えば、本やおもちゃ箱は棚にしまって、カーテンをかけると良いでしょう。ものが見えなくなると、部屋がスッキリして見えます。できるだけ刺激の少ない教室にして、子どもが集中しやすい環境に整えましょう。
2.周りの子どもに理解を求める
ADHDの子どもを担当したとき、同じ教室の子どもたちにも理解を求めましょう。
子どもが保育園で過ごすとき、1番長く一緒にいるのは同じ教室の子どもたち。同じクラスの子どもたちがADHDの特徴を知れば、ADHDの子どもが過ごしやすくなるだけでなく、子どもたちみんなが「人にはそれぞれ苦手なことがある」と勉強できます。
ただし、詳しい症状や特徴を言っても理解できません。例えば、ADHDの子どもが騒いでしまったとき、「わざとじゃないんだよ」「これ貸して、じゃなくてオモチャ貸してって分かりやすく伝えてあげて」などフォローを入れることからはじめましょう。
「苦手なことを助け合う」という気持ちを、子どもたちに伝えることがポイントです。
3.他にも担当する先生がいる場合、接し方を共有する
他にも同じ教室を担当する保育士がいたら、ADHDの子どもへの接し方を共有しておきましょう。
保育士によって対応の仕方が違うと、子どもがギャップを感じて、混乱してしまうからです。
「騒いでいるときは、どのように注意しているか」「約束が守れたら、どのようにほめるか」など、具体的な対応を伝えておきましょう。違うクラスを担当する保育士でも、園外保育のときADHDの子どもに接する可能性があります。同学年を担当する保育士には、接し方を共有しておくと良いでしょう。
以上が、ADHDの子どもにできる集団的な支援です。保育園や幼稚園で集団的な支援ができれば、ADHDの子どもだけでなく、保護者も安心して通うことができます。
もし、1人で対応するのが大変だなと思ったら、周りの先輩や園長にも相談するのも良いでしょう。
[quads id=1]
保護者への支援
最後に、ADHDの子どもを担当するときは、保護者へのフォローも行いましょう。
保護者へのフォローは、主に次の2つです。
- 園で遊んでいる様子や成長を、細かく伝える
- 保護者の悩みを聞いておく
それぞれ説明していきます。
1.園で遊んでいる様子や成長を、細かく伝える
ADHDの子どもを担当したら、保護者には子どもが園で遊んでいる様子や成長を、細かく伝えてあげましょう。
ADHDの子どもを持つ保護者は、「今日は暴れていないかな」「誰かをケガさせてないだろうか」と心配ごとが多いもの。
そこで、「今日は自分から一緒に遊ぼうって言えましたよ」「体を動かすのが大好きで、ずっと追いかけっこをしてました」と、子どもの様子を細かく知れると、安心できます。
保護者が見られない分、園でのできごとや子どもの成長をしっかり伝えてあげましょう。
2.保護者の悩みを聞いておく
ADHDの子どもを担当したら、保護者の悩みをしっかり聞いておきましょう。自分の理想の子育てとのギャップに悩んでいる保護者が多いからです。
例えば、保育園での子どもの様子は包み隠さず伝えた上で、「何か家で困っていることはありませんか?」と会話してみましょう。
もし「外で遊ぶだけじゃなく、たくさん本も読んでほしいのに、おとなしく座れない」と保護者が悩んでいたら、「〇〇くん、体動かすのが大好きですもんね。園でも読み聞かせを行なっているので、少しずつ興味のある話題を探してみます。」と園でできる対応を伝えましょう。
さらに「何か家で興味を持っていることがあれば、教えていただけますか?」と協力して子どもを育てていこうという姿勢があれば、保護者も信頼してくれます。園での対応も考えやすくなるので、ADHDの子どもを担当したら、保護者の悩みをしっかりヒアリングしましょう。
以上が、ADHDの子どもを持つ保護者への支援です。保護者へのフォローができると、信頼してもらえると同時に、子どもへの接し方も共有できます。保護者と園が一体となり、同じ方針で子育てをするようにしましょう。
まとめ

ADHDの子どもへの接し方や、対応方法について説明してきました。
ADHDは発達障がいのひとつ。本人の性格や保護者の育て方、しつけが原因ではありません。しかし、理解されにくい障がいのため、とても誤解されやすいのです。
大切なことは、本人への支援だけでなく、園を巻き込んだ支援や保護者への支援も行うこと。とくに、ADHDの子どもは誤解を受けて叱られやすく、自己肯定感が低くなりやすい傾向があります。子どもによって個人差もあるので、まずはしっかり子どもを観察し、保護者や先輩と協力しながら対応してみましょう。
対応方法を参考にして、子どもにとってもあなたにとっても素敵な時間を過ごしてくださいね。









